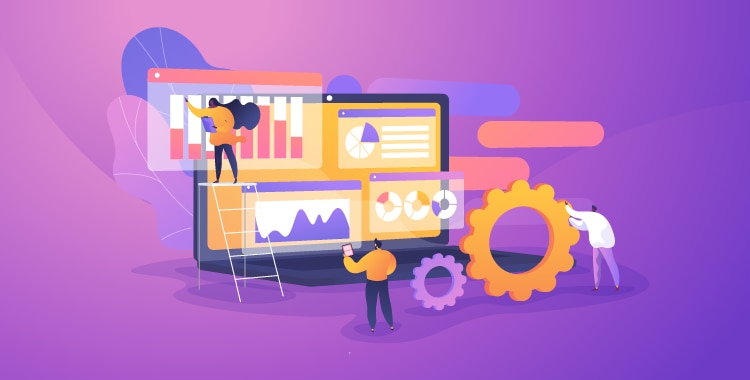
PRMで記録されている“支援ログ”とは何か?──支援がデータになる時、組織は何を読み解けるのか
前回は、米国のチャネルマネージャー/パートナーサクセスマネージャーが、
“成果を出す代理店を支援する”という仕事をどのように定義し、日々何に取り組んでいるのかを紹介しました。
今回はさらに一歩踏み込み、その支援を「ログとして残す」PRM(Partner Relationship Management)は何を記録しているのか?
そして、そのデータから組織は何を読み取り、どう活かしているのかを具体的に解説します。
「支援」を“見える化”すると、何が残るのか?
営業行動はSFAで、マーケティング活動はMAでログ化されるのが当たり前になった今、
「支援」だけが属人的で、痕跡のない業務として取り残されている──
その問題を解決するのがPRMの役割です。
では、PRMはどんな行動を、どんな粒度で記録しているのか?
以下に、実際に多くの米国企業で活用されているログ項目の代表例を挙げてみます。
PRMで取得される主な“支援ログ”の項目と意味
ログ種別 | 内容の例 | 意味すること |
|---|---|---|
資料閲覧ログ | 代理店ごとの資料開封日時/閲覧ページ/滞在時間 | 支援資料が届いたか、活用されたか、どこで離脱したか |
トレーニングログ | 登録・受講・完了・テストスコア | 理解度・受講率・習得状況の把握/営業現場の準備状況の判断 |
提案ツール利用ログ | 提案テンプレのダウンロード数/使用頻度/バージョン別利用状況 | 現場でどの支援ツールが使われ、何が使われていないか |
FAQ・ナレッジ検索ログ | 検索キーワード/閲覧数/未解決率 | よくある疑問/サポートニーズ/情報設計の改善点が見える |
PRMログイン頻度 | 期間別アクセス数/最終ログイン日/滞在時間 | パートナーのエンゲージメント可視化/休眠検知の指標 |
キャンペーン参加ログ | 招待→反応→参加→資料ダウンロード→フォローの一連ログ | 支援施策に対する関心と消化率のモニタリング |
ログが“KPI”に変わる瞬間
単に「資料を見た/見ない」だけでは、KPIにはなりません。
PRMが強力なのは、“ログの連鎖”をスコアとして構造化できる点にあります。
たとえば:
【支援消化スコア(Support Engagement Score)】
- トレーニング完了:25点
- 提案書ダウンロード:15点
- 資料閲覧完了:10点
- FAQ利用:5点
- ポータル連続アクセス3日以上:+5点
というように、各支援アクションに重みづけをし、
“どのパートナーが、どれだけ支援を使ったか”をスコアで横並びに評価できるようになります。
このスコアが一定以下の代理店はアラート対象とし、
逆にスコアが高い代理店を「ロールモデル候補」として事例化・横展開していきます。
ログの“見方”が組織の判断を変える
では、ログをKPI化することで組織はどのような“判断”ができるようになるのでしょうか?
1. 成果と支援の相関を確認できる
例)「トレーニング完了率80%以上の代理店は、商談化率が平均2.8倍」
これにより、「支援の有無」ではなく「支援の消化状況」が成果に与える影響を定量的に評価可能に。
2. “沈黙しているパートナー”の発見が早くなる
例)「ログインが30日間途絶えており、支援消化スコアが下位25%に沈んでいる代理店を週次で抽出」
関係性の薄れた代理店を早期に検知し、フォローアップを自動化できる。
3. 支援コンテンツの改善につながる
例)「FAQのうち、ある2つのページだけ直帰率が高い」
→ 内容の再編集、動画化、ナレッジ統合などの判断に活用。
PRMログは「支援のPDCA」を回すための設計図
日本企業の多くでは、支援は“やって終わり”“配って終わり”で、その後の追跡ができていない状態が続いています。
ログがなければ、評価も改善も再現もできない。
これは、営業やマーケティングでSFAやMAが登場する以前と似た状況です。
PRMのログは、その支援活動における「A/Bテスト」「ターゲティング」「リテンション改善」を可能にします。
つまり、支援を「感覚」から「戦略」に引き上げるための、前提条件としてのインフラなのです。
おわりに:ログは、支援を“語れるもの”に変える
代理店の「やる気」や「関係性の良し悪し」で評価されてきた支援活動を、
誰が何を見て、どこで離脱し、何が使われているかをログで把握することで、初めて“語れる業務”になります。
そしてその語られたものが、KPIに、評価に、改善に、組織の未来に接続されていく。
支援が主観を脱し、再現され、広がっていくために──
最初に変えるべきは、“何が記録されているか”です。
👉関連記事



