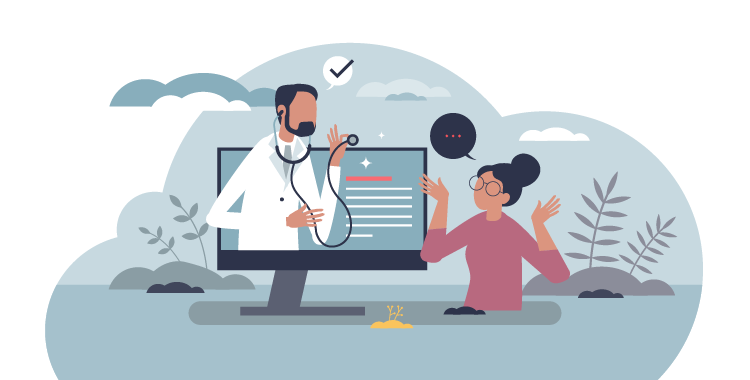
あなたのチャネルは健康ですか?──代理店全体を“診断”するための観点とスコア設計
「最近、案件の出る代理店が偏ってきてるな…」
「提案数は一定あるけど、なんとなく勢いがない」
「チャネル全体が“縮んでる”気がするけど、確証がない」
そんなモヤモヤを感じたことはないでしょうか?
代理店チャネルを構築・運用していると、
個別代理店の様子は把握できても、“チャネル全体の健康状態”はつかみにくいものです。
本稿では、チャネル全体を“診断”するという視点から、構造的な評価観点とスコア設計の考え方を整理します。
なぜ「チャネルの健康診断」が必要なのか?
まず前提として、代理店が複数社を扱うのは合理的な行動です。
理由 | 背景 |
|---|---|
成果だけを見ていると、“静かに死んでいる代理店”を見落とす | 提案も反応もなく、実はすでに動いていない |
好調な代理店にリソースが集中し、他が放置される | 「偏り」はやがて「依存」に変わる |
全体感がつかめず、支援が“場当たり”になる | 「どこが健全で、どこが危ないのか」が見えないまま運営されている |
チャネル診断の基本設計:3つの観点 × スコア化
【観点①】 “活動量”のスコア(=どれだけ動いているか)
指標例 |
|---|
提案数・資料DL数・問い合わせ件数 |
教育コンテンツの受講数 |
営業との定例接触頻度 |
→ 「表に出てくる行動」の総量を捉える指標
【観点②】 “成果量”のスコア(=どれだけ結果が出ているか)
指標例 |
|---|
案件化数・成約件数・売上金額 |
キャンペーン連動での成果発生 |
再購入・継続提案率 |
→ 「行動の先にある結果」を捉える指標
【観点③】 “関係性”のスコア(=どれだけ関与し、意欲があるか)
指標例 |
|---|
主担当者との連携頻度(定例/非定例) |
支援施策への反応(フィードバック提出、アンケート回答など) |
自社イベントや研修会への出席率 |
提案スクリプト/資料の“自社化”度合い |
→ 「温度」や「関係の厚さ」を定量的に見ようとする指標
スコア設計イメージ:レーダーチャート or 4象限
以下のような分類でチャネル全体を可視化することで、重点支援/育成/放置/撤退の判断がクリアになります。
活動量 | 成果量 | 関係性 | ステータス分類 |
|---|---|---|---|
高 | 高 | 高 | 主力(維持+共創) |
高 | 低 | 低 | ポテンシ ャル(重点育成) |
低 | 低 | 低 | 非アクティブ(再エンゲージ or 撤退) |
低 | 高 | 低 | 非常勤主力(関係強化が必要) |
スコアを使って“健康状態”を見抜くサインとは?
チャネルの兆候 | 健康診断で見るべきサイン |
|---|---|
案件が偏ってきている | 上位層への依存度が高まっていないか?(上位5社の構成比) |
動いている代理店が固定化している | 新規層/準主力層の”活動量は十分か? |
育成しても成果が出ない | 関係性スコアが低い=“本気で動こう としていない”可能性 |
手応えはあるが成果に繋がらない | 成果スコアが低い=支援内容と市場ニーズがずれている |
スコア運用のコツ:「精緻にやらない」「定性を混ぜる」
- スプレッドシートで月1回の更新でも十分
- 点数化より「3段階(高・中・低)」くらいのざっくり分類でOK
- 定量ログ(案件数・DL数)+ 定性観察(会話の雰囲気・支援反応)で補完する
“診断しやすい形”にすることで、運用が続くスコア設計を目指しましょう。
最後に:成果を出していても、チャネル全体が健全とは限らない
チャネルとは、“現在の売上”だけを支える装置ではありません。
“持続可能な提案構造”をどう維持・育成していくかが本質です。
だからこそ、必要なのは:
- 健康な代理店と、そうでない代理店の違いを明らかにする視点
- リスクの兆候を事前に察知できる観察力
- 支援を“構造で見直す”ための共通言語(スコア)
「なんとなくの手応え」から脱却し、
診断し、判断し、優先順位をつけることで、
チャネル全体の“体力”を取り戻すことができます。
👉関連記事



