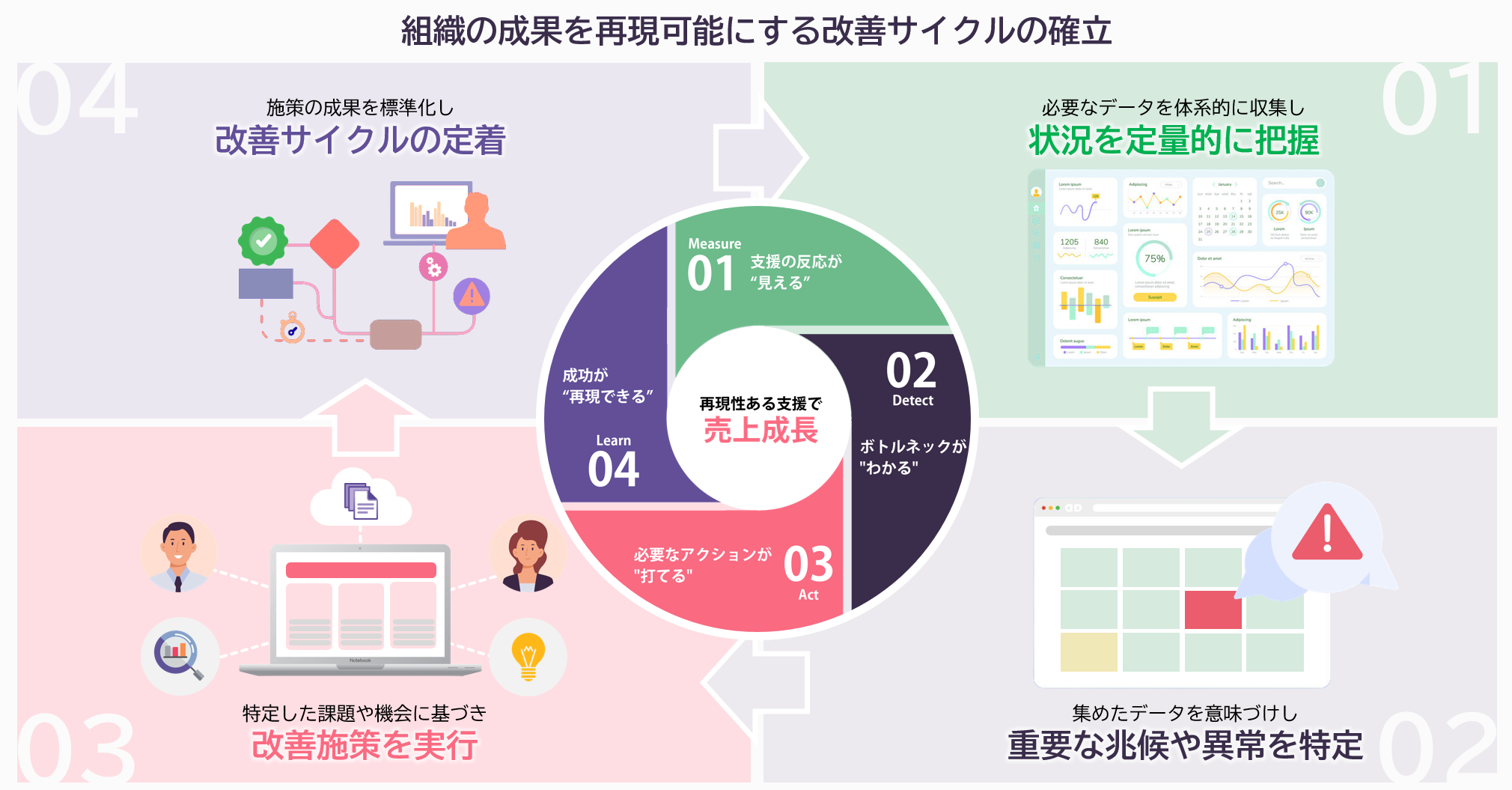代理店は別商材を提案できていますか?──クロスセルを仕組み化するチャネル設計戦略
「あの代理店は主力商材は動かしてくれるけど、それ以外はまったく扱われていない」
「製品ラインナップは複数あるのに、実際に提案されているのは一部だけ」
「売れていない商材を動かすには、どう支援すればいいのか……」
そんな課題を抱えているベンダーは少なくないはずです。
アップセル(同製品の上位プランへの移行)と違い、
クロスセル(別商材の提案)は“別の支援設計”が必要になります。
本稿では、代理店によるクロスセルを“偶発”ではなく“仕組み”として回すためのチャネル設計視点をお伝えします。
なぜクロスセルは提案されないのか?
障壁 | 背景にある構造 |
|---|---|
商材数が多くて覚えきれない | 製品ごとに提案資料や支援内容が分断 |
どの顧客に何を提案すればいいか分からない | ターゲティング支援が不十分/レコメンドが曖昧 |
実績がないから提案に不安がある | 成功事例の社内共有が不足/事例集が整っていない |
売っても評価されにくい | インセンティブが初回商材や主力製品に偏っている |
クロスセルが回ると、チャネルの“厚み”が生まれる
- 1社あたりの売上が増える(売上密度の最大化)
- 単品依存のリスクが減る(提案分散による安定性)
- 代理店が“自社理解が深いパートナー”へと進化する(関係性の深化)
→クロスセルは、売上拡大 × エンゲージメント深化の両輪
クロスセルを仕組み化する5つの設計ポイント
【1】“誰に・何を”が明示されたレコメンド設計
- 顧客属性/業界/利用状況に応じた商材マッピング
- 例:「A商材導入済みの○業種には、B商材を次に提案すべき」
- 代理店ポータルや定例レポートに“提案候補”を自動で提示
→ クロスセルは、“次にやることが決まっている”状態にして初めて回る
【2】トークと資料を“顧客視点”で再構成
- 「この機能もあります」ではなく、「こういう課題にも使えます」
- 一括資料ではなく、既存導入商材からの拡張ストーリー型資料
- 例:導入済Aの“課題未解決ポイント”を引き金に、Bを紹介する構成
→ 商材ではなく「課題接続」で提案させるのがコツ
【3】代理店内で“扱える人”を増やす教育設計
- クロスセル商材のLMS講座を「A商材受講者限定」で出す
- 商材ごとに“サマリだけで動ける”短縮版スクリプトを整備
- 代理店内に「横展開できる担当者」が育つ構造を用意
→ 提案が“その人で止まっている”状態を崩すことがカギ
【4】クロスセル提案に特化した報酬・可視化制度
- 商談登録時に「追加提案」「別商材提案」が明記される設計
- クロスセル発生数のランキング/月次レポート共有
- インセンティブも“製品横断的な評価”で設計
→ 売上よりも“提案アクション”を評価軸に含めることが重要
【5】“提案しない理由”をなくす仕掛け
- よくある疑問へのFAQテンプレ(例:「この商材って導入難易度は?」)
- 事例の“セリフ化”(例:「この顧客、最初はこう言ってました」)
- 初回提案時に“次に提案すべきもの”をセットにして渡す
→ 提案のボトルネックは、「知らない」「怖い」「面倒」の3点セット
→ それをUXで自然に潰す
実務に落とすステップ(例)
- 商材別のクロスセル対象リストを定義(プロダクト同士の相関整理)
- クロスセル導線(LMS・資料・通知)を1ページにまとめる
- 代理店内受講率・提案率・商談化率を3ヶ月単位で可視化
- 成果事例を「クロスセル起点の成功体験」として再編集
- クロスセルKPIを組み込んだ代理店ランキングや表彰制度の設計
最後に:“別商材”は、別支援で動く
主力商材は、支援しなくても勝手に動く。
でも、それ以外の製品は、「誰に・どう話すか」の設計がなければ動かない。
クロスセルは、代理店任せにしてはいけない領域です。
UX・提案導線・評価設計を通じて、「提案されやすい環境」が整ってこそ、
チャネル全体の売上は“面”として拡大します。
売れていない製品の責任は、製品ではなく構造にあるかもしれない。
👉関連記事